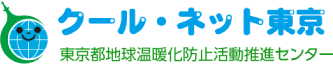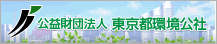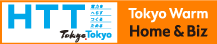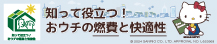よりよい未来をつくるために、再エネ電気について考えてみよう
はじめに
よりよい未来をつくるために、再エネ電気について考えてみよう。
たべるものと同じように電気も選ぶ時代。
農地から自然エネルギーの電気が届くことを知っていますか?
“電気にだって生産者がいる”
営農型太陽光発電 農業と発電に取り組む人がいて再エネ電気を届ける人がいる。
“再エネ電気を選ぶ”
1人ひとりの選択が、アクションが、未来を変えられる。
今回は、二本松営農ソーラーの近藤さんとハチドリソーラーの池田さんに
『再エネ電気の魅力』や『実現できる未来』についてお話しいただきました。
登壇者
営農型発電事業者

二本松営農ソーラー 株式会社
代表取締役
近藤 恵 さん
再エネ電力供給事業者

株式会社ボーダレス・ジャパン
ハチドリ電力
代表
池田 将太 さん
インタビュー
近藤: 2006年から私はここ、福島県二本松市で有機農業をずっとやってきました。3.11の東日本大震災による原発の事故によって一度私は廃業を余儀なくされ、その後「やはり自分たちの手で再生可能エネルギーを作らなければ非常にまずいことになる」というふうに思ったのがきっかけで
ソーラーシェアリング(営農ソーラー)
に取り組んでいます。
自分の蔵にはお米があったし、水も水道や井戸から汲んでいましたのでこれは心配ないなと思っていたんですけれども、エネルギー源がないのでトラクターとか軽トラが1cmも動かせなくて、地方は非常に弱いんだなと。
今までは、地方は食べ物もエネルギーも非常にふんだんにあるというふうに勘違いしてたところがあります。
これからは農業者が中心となってエネルギーを作り出す時代が創れるのではないかなという思いを込めて、この「ソーラーシェアリング」を始めました。
太陽光パネルと空間を適度に空けることによって下の作物も育つし発電もできる、という仕組みになっています。ここからちょっと離れたところに垂直ソーラーというのがあるんですけれども、
垂直ソーラーですと上空が開いていて列幅も十分に広く、
大型農業機械の操作がしやすいという利点があるので、これから非常に有望な
技術というふうに私たちは捉えています。



池田: 僕は大学に入学してから国際協力と出会って、ミクロネシア連邦という大洋州のすごく小さな島国で活動していたんですけど、ある日、友人の家が気候変動による海面上昇で流されるということが起きました。「気候変動で本当に生活ができなくなるっていうことがあるんだ」と目の当たりにし、この問題に人生をかけようと決めました。
CO₂の排出量が最も多い電気が気候変動のすごく大きな要因だってことを知り、「エネルギーを通じて気候変動の解決をしよう」とハチドリソーラーという事業を創業しました。その後、自然エネルギー100%の電気だけを届けるハチドリ電力という事業も行っています。
僕らがとても大切にしているのは、社名にある『ハチドリのひとしずく』という童話の物語で、山が山火事で燃えてしまって、森の動物たちは我先にと逃げていく中で、世界で1番小さいハチドリが、水のしずくを1滴ずつ山にかけていくんですよね。森の動物たちから、「そんなことやっても意味ないじゃないか」って言われてしまうんですけど、ハチドリは「私は私にできることをしてるだけ」と言って水をかけ続けるという物語です。
電気を自然エネルギーに変えるということはすごく小さなことだけど、「微力だけど無力じゃないよね」っていうことを大切にしながら、みんなで自然エネルギーを使っていくことが当たり前の社会づくりに取り組んでいます。
池田: 僕らハチドリ電力は自然エネルギー100%の電気だけを提供する電力事業をやっていますけど、電気を再生可能エネルギーに変えることは、気候変動に対して1番身近で1番手軽にできることです。3分の手続きで電気を変えられて環境にいいアクションができるって、本当にいいところだなと思っているのが1つ目です。
もう1つは、近藤さんのような、ソーラーシェアリングという発電方法で作った電気を、手触り感を持って家で使うことができる、そういう環境に対しての安心感っていうのがあるのも、再エネのすごくいいところだなと思っています。

二本松営農ソーラー 株式会社
近藤: 送り出す側の私たちも、作り手の電気を届けてくれるという方に買っていただけるっていうのは大変ありがたい話です。
「農地につけて大丈夫なの?」っていう声も正直あるんですよ。でも見てください。パネルとパネルの間は70%ぐらい空いてるんです。そうすると下に十分日光も届くし、一番顕著なのは夏場ですね。パネルが作る適度な日陰で、牛や農作物を守るという物理的な役割も担っているんですよ。
それから自分たちの手で設計できるのもいいところですよね。今までエネルギーというのは誰かにお任せしてたんだけども、自分の農場でこのように設計するというこの手触り感が、やはり再エネのいいところの1つだというふうに思います。
池田: 確かにそうですね。環境を壊すような大規模集約型が多かったところから、近藤さんのように 分散型 で、環境第一に考えた発電所が広がっていくってすごくいいことですよね。
池田: 電気を切り替えること自体、結構大掛かりなんじゃないかって思われることがあるんですけど、今の既存の電線からそのまま切り替えることができますし、手続きはウェブで3分しかかからないです。戸建てでもマンションでもすぐ変えられるので、安心してもらいたいなと思っています。
料金も、再エネって高いんじゃないのかと思われがちなんですけど、逆に再エネに切り替えたことで、電気代が安くなってる方もたくさんいます。再エネだから高いってことが絶対じゃないので、そこも安心して是非使ってもらいたいなと思っています。
近藤: 作り手側がよく受ける質問は、「太陽光パネルのリサイクルどうなってるの?」というものなんです。
まず、廃棄量の問題から言うと、車のスクラップの量から比べればものすごく少ないっていうことがまず1つ。
もう1つは、今リサイクル技術が非常に発達しています。南相馬のリサイクル工場に自分の目で見るのが大事だなと思って行ったんです。そしたら、もうガランガランで。ビジネスになるからリサイクルパネルが早く来ないか待っているんですよ。それに、すごく技術が発達していて、アルミとガラスをかなり綺麗に分別できるんです。リサイクルの精度が上がってるんですね。これは非常に安心できるファクターだなと思いました。
近藤: やっぱり私は農業をやっているということもあって、未来は農業と同じ、その果実を選び取るまで時間がかかるというふうに思っています。
このパネルもそうなんですけれど、大体設備寿命は30年ぐらいなんです。だから設備を設置して「はい終わり」ではないんですよね。これを守り育てていくっていうことが必要です。
太陽光パネルは太陽の光をエネルギーに変えるという素晴らしい装置なんです。植物もそうですよね。木を植えて果実をもらうまでは結構時間がかかる。だけど太陽光発電はそれに比べればそんなに難しいことではないというふうに思うんですね。
これを農業者がやるようになったら、あるいは地域の人たちが自分の手でできるようになったら、どんなに豊かな世界が待ってるんだろうと思います。それが
分散型
であったり、安心感があったりというエネルギーの形なので、これを選ばない未来はないなというふうに思います。
池田: 僕は電気って投票だなって思っていて、自分がどの電力会社、どんな電気を選ぶのか、毎月支払う電気っていうのはどんな場所に使われるんだろうか、どんな人に払われるんだろうかっていう消費の選択ができる、すごく大きなものだと思ってます。


池田: 100年先も1000年先も持続可能な、今よりもっといい社会を残していくこと、みんなでそういう未来を選んでいくために自然エネルギー、再生可能エネルギーを選ぶことっていうのは、とても大切なことだなと思っています。
今、地球温暖化はどんどん深刻化してしまって、今年の夏の人工芝の温度は70度近くいきました。子どもたちが本当にこれから先もサッカーや野球ができるんだろうかと思った時に、やっぱり難しい。でも、今まで当たり前だったことが、今まで以上にいい未来に繋がっていくっていうそういう選択を、電気を通じてしていきたいなと。
自分が電気を変えて本当に社会って変わるんだろうかっていうと、もしかしたらそれだけじゃ変わらないかもしれない。でも、やらないよりやった方がいいことだし、微力だけど無力ではないことだと思ってるので、マンションに住んでる人も戸建てに住んでる人も、自分が再生可能エネルギーを選ぶっていうその選択で、いい未来をみんなで創っていけたらいいなと思っています。

キーワード
作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できます。
(出典:農林水産省)
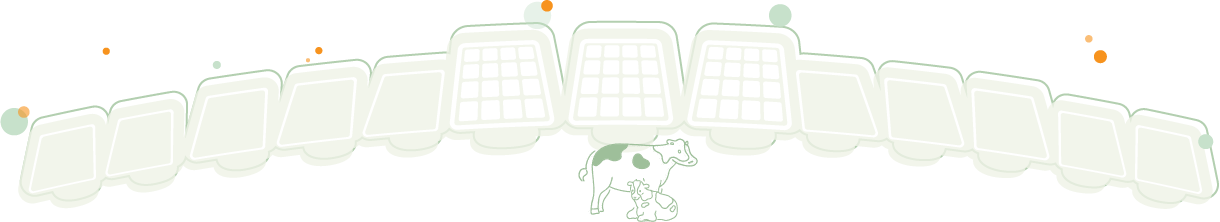
お問い合わせ
普及連携チーム
【受付時間】平日 9:00~17:00
電話:03-5990-5065